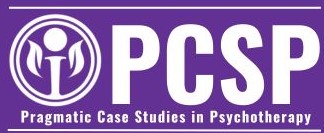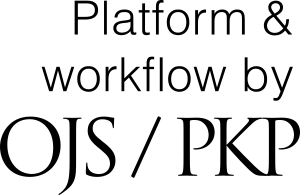描画による感情表現と正しい言葉による対応がもたらす非連続的変化
DOI:
https://doi.org/10.14713/pcsp.v11i4.1936Keywords:
パーソナリティ障害, 描画, 正しい言葉での対応, 非連続的変化, 介入技術の伝承Abstract
本事例研究は,パーソナリティ障害,統合失調性情動障害,非定型の精神病等の診断がつけられるほど重症であったクライエントが,描画を媒介としたセラピストとのやり取りの中で劇的に軽快したプロセスを詳細に検討したものである。私は心療内科医としてこの事例の重篤さに驚くとともに,行動療法家として日頃行っている査定や介入との異同を念頭に読み進めていった。事例報告の方法としては,「臨床家による語りの形式」をとっており,標準化された量的質問紙も効果判定に使われなかったとされているが,実は行動療法における単一事例実験計画と原理的な面で相違点よりも類似点の方が多いと思われる。本事例の介入は,描画とそれを媒介として成立したコミュニケーションによって行われたが,その中核は「描画による感情表現と正しい言葉による対応」と理解できる。介入が進むにつれて,描画とそれを描いたクライエントの中に「意識的努力をしないのに」非連続的な変化が生じたことが明らかになったが,それがどのような機序によってもたらされたのかを次に考察した。そこでは,連続的な変化を前提とし,機能分析というアセスメント法に基づいてひとまとまりの行動に介入をする行動療法とは対照的に,生活や人生の文脈自体が介入の対象とされ,新たな文脈を規定する初期条件と拘束条件を設定することによって介入が進められているものと想定された。そして本事例では,治療者の「目前の課題をよく把握してからそれに適合する方法を適用する」というアセスメントが初期条件となり,描画という自己表現をするための構造と,治療者のどんな場合にも逃げない率直な対応や返答がぶれない拘束条件を作り出したことが,決定的なセラピー促進要因になったと考えられた。最後に,本来治療者個人が「人生の行路に沿って時間をかけて積み上げていくほかない」介入のための技術が,いかに伝承されていくのかという点に注目し,事例研究の持つ機能にふれて,本論文の結びとした。
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright for articles published in this journal is retained by the authors, with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use, with proper attribution, in educational and other non-commercial settings. The author has agreed to the journal's author's agreement.

All articles in this journal are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.